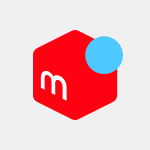Alexander Sergeievich TANEYEV
( 1850 ~ 1918 )
収録曲 & 演奏者
①交響曲 第2番 変ロ短調 作品 21
②組曲 第2番 ヘ長調 作品 14
ウェルナー・アンドレアス・アルバート:
指揮
フィルハーモニア・フンガリカ
録音:1986 年
MARCO POLO:8.223133(輸入盤)
アレクサンドル・セルゲイェーヴィチ・タニェエフ(タネイエフ、タネーエフとも。三省堂の『クラシック音楽作品名辞典』では「タニェエフ」を採用しています)は、少しは有名な作曲家・音楽理論家セルゲイ・イヴァノヴィチ・タニェエフの遠縁にあたる人です❗
チャイコフスキーに学び、弟子にスクリャービン、ラフマニノフ、グラズノフ、プロコフィエフ、メトネルなどがいるのは、セルゲイの方です。注意してくださいね。
A . S . タニェエフはロシア国民楽派の作曲家で、リムスキー=コルサコフに作曲を師事しています。官僚としても活躍したようで、ロシアの地理学会民謡部長を勤めています。ロシア民謡の収集・研究に、情熱を燃やしたのですね。タニェエフにより採譜された民謡は、後に編曲され、リャードフによって出版されました(近いうちに、リャードフも出品します)。
A.S.タニェエフはいくつかの歌劇を作曲したそうですが、ひとつとして今日までレパートリーの中に生きのびているものはないみたいです。ほとんどの作品は性格が軽く、すべての作品が他の有力な国民楽派の作曲家(例えば、リムスキー=コルサコフやバラキレフ、リャードフ)の影響を示しているそうです。
当盤は記憶に間違いがなければ、世界初録音だったと思います(今でも唯一かな❓)。「ひょっとすると、この1枚の CD がきっかけとなって、S . I . タニェエフの知名度と逆転することもあり得るほどの、それほどの傑作です」とか何とか、書かれていた気がします。
確かに透明感と哀感が一体化したロシア交響曲ですが、チャイコフスキーの亜流の感は拭いきれません。が、これほど美しく哀しく充実した亜流なら、見逃す手はありません。お楽しみください。
盤面に、傷はありません。
素人検品です。傷の見落としがあっても、ご容赦願います。
解説書に、少し汚れがあります。
写真を必ずご確認願います。
神経質な方は、ご購入を控えてください。